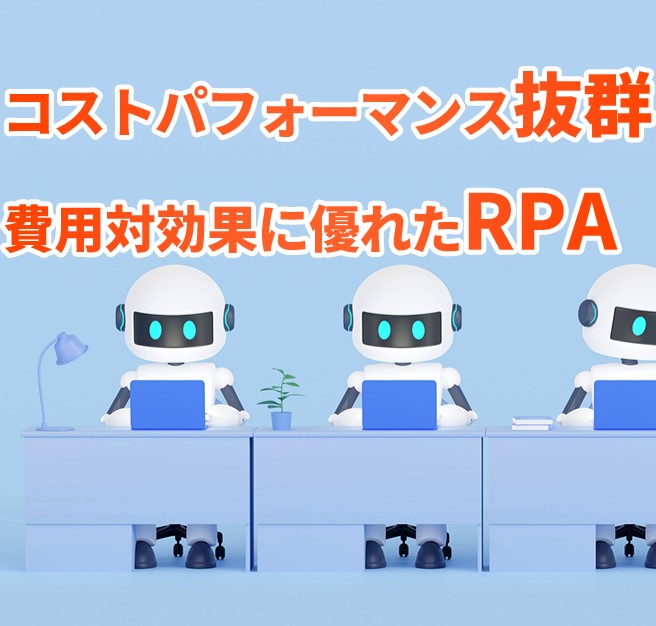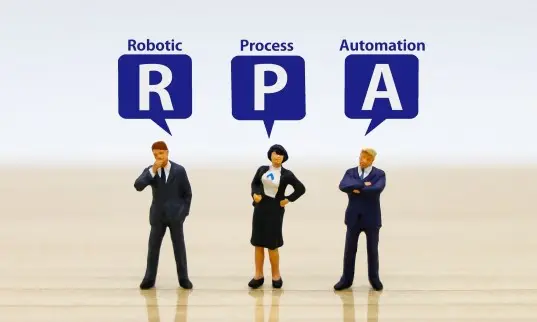業務効率化とコスト削減を実現するRPA受託開発サービス。低コストで高品質なRPAソリューションを提供し、企業の成長をサポート! 採用難や業務自動化などの効率化をお考えの方はこちら
RPA内製化と外注の違い
内製化と外注(委託)それぞれの特徴を知ることで、自社導入に最適な選択を検討できます。
RPA導入にあたっては、自社の人材を活用しノウハウを社内に蓄積する「内製化」と、専門ベンダーを頼り効率的な「外注」のいずれか、または両方を組み合わせて進めるかが大きな分岐点になります。短期間で成果を出したい場合や、社内のリソースが乏しい場合には外注を利用する利点が高いです。しかし、長期的に運用ノウハウを蓄積して企業のDXを推進したいと考えるなら、内製化が効果的といえます。コストや育成面の見通しを踏まえたうえで、どちらが自社に合致するかを見極めることが重要です。
内製化の定義と特徴
内製化とは、自社の人材でRPAツールを使いこなしながら、設計・開発・運用までを一貫して行う手法です。社内の担当者が企画段階から深く関わることで、RPAの活用方針を柔軟に調整することができます。外部に依頼せずに進めるため、コスト増を抑えながらリアルタイムで改善や修正を行いやすいのが利点です。一方で、社内で人材を育成する期間や学習コストが必要になる点は、導入時に考慮しておく必要があります。
外注(委託)の特徴
外注(委託)では、専門ベンダーが持つ高い技術力や豊富な経験を活用することで、比較的短期間で成果を得ることができます。高度なカスタマイズや複雑なシナリオを短期集中で実装できる可能性が高まる一方、開発や運用ノウハウが社内にたまりにくいという側面もあります。また、外部ベンダーに委託する以上、追加の要望や運用開始後の修正に別途費用が発生するケースもあるため、長期的なコスト管理が欠かせません。
業務効率化とコスト削減を実現するRPA受託開発サービス。低コストで高品質なRPAソリューションを提供し、企業の成長をサポート! 採用難や業務自動化などの効率化をお考えの方はこちら
RPA内製化のメリット
内製化にはコスト面や対応の柔軟性など、さまざまな利点があります。
RPAを内製化する最大の魅力は、社内で培った知見を自社の将来に活かせる点にあります。開発担当者が業務フローを深く理解しながらロボットを構築できるため、細部まで最適化されたRPAシナリオを作り上げることが可能です。さらに、外部委託にかかる費用や調整負担を削減できることから、長期的に見ればコストメリットが得られるでしょう。加えて、内製化はDX人材を育てる絶好の機会でもあり、企業全体のデジタルシフトを加速させる原動力となります。
コスト削減と迅速な対応
外部のベンダーやコンサルタントへ依頼する際の初期費用や月額の運用費を抑えられる点は、大きなコストメリットといえます。加えて、緊急の修正や小規模な改修を素早く行えるため、トラブル対応や業務変更が生じた際にも柔軟に対応できます。中長期的には、こうした機動力が業務効率を高めるうえで効果的な要素となります。結果的に、経費削減だけでなく組織全体の反応速度向上にも寄与します。
ノウハウ蓄積とDX人材の育成
内製化によって得られた経験やスキルは、単にRPAにとどまらず企業のIT活用全般に役立つ財産となります。自社スタッフが習得したRPA開発プロセスやエラー対処法などは、DX推進のための汎用的なナレッジとして広く活用可能です。こうしたプロセスを通じて、新たな業務領域にも挑戦できる人材が育ち、企業全体のデジタル人材不足の課題にも対応しやすくなります。
セキュリティ面でのリスク軽減
RPA運用では、対象業務に関連した顧客データや社内の機密情報を扱う場面も少なくありません。開発から運用までを社内完結できる内製化の形態であれば、データが外部に渡るリスクを大幅に抑制できます。セキュリティポリシーを自社の基準に合わせやすい点も大きな利点であり、情報漏えいや不正アクセスに対してより万全な対策を講じやすくなります。
RPA内製化のデメリット
内製化にはメリットだけでなく、足元のリソース不足や育成面の課題もあります。
社内でノウハウを蓄積するという利点の裏には、担当者の学習コストや手戻りの発生リスクが存在します。ツールの操作性やスクリプトの書き方が理解できていない状態で開発を進めると、トラブルや修正が繰り返される恐れもあり、かえって導入が長期化するケースがあります。また、育成に伴うスキルギャップを埋めるための研修費や時間を確保するのも容易ではなく、プロジェクトの進行管理が難しくなる点も見逃せません。
RPAの習得に時間が必要
RPAツールの機能理解や業務のプロセス分析を習得するには、技術的な勉強と現場とのヒアリングが欠かせません。初めてRPAを扱う担当者にとっては、プログラミングやシステム設計の基礎を学ぶ時間を確保する必要があります。さらに、ツールを使ったロボット開発だけでなく、障害時のトラブルシューティング能力も重要です。こうした知識の定着には継続的なトレーニングや実践が求められるため、社内リソースに余裕を持たせることがポイントになります。
昨今では、直観的に操作できるRPAツールであっても、実際に業務に適用し安定稼働させるには一定の練習や試行錯誤が必要です。表面的な操作手順を覚えるだけでは十分でなく、ロボットが正しく動作するためのロジック理解や業務フローの最適化も行わなくてはなりません。こうした習得期間が長引くと、導入初期のROIが低下する可能性もあります。結果として、早期に効果を求めるプロジェクトほど人員やスケジュール管理に工夫が必要になるでしょう。
人材の育成に時間が必要
RPAを内製化するには、開発者の技術的スキルだけでなく、現場とのコミュニケーション力や業務分析力も不可欠です。ちょっとエクセルなどのオフィスの扱いが上手な方でも適正がなく、うまくいかないケース新たな人材を雇用しても、即戦力として働けるまでの教育や研修には一定の期間を要します。
既存社員を育成する場合でも、普段の業務と並行して学習を進めることになるため、負担も大きくなりがちです。このような取り組み方は中途半端で、なかなかスキルが定着しません。 また育成しても、異動や退職などで離脱ということも考えられます。
こうした育成コストを長期的な投資と捉えられるかが、成功に向けた大きな分岐点となります。
開発・運用に工数がかかる
RPAを内製化する上で、開発から運用までの負担が大きくなる点はよく挙げられます。
自社内で開発を進める際には、プロジェクトの管理やスケジュール調整など、事前に配慮すべき作業量が多く発生します。業務フローに合わせたカスタマイズを行うためには、開発担当者だけでなく現場が連携し、要件を明確にしていく必要があります。運用段階でも、トラブル発生時の原因特定や修正対応に追われることがあり、安定稼働までに時間がかかるケースも少なくありません。したがって、内製化を進める場合は十分な工数計画と保守体制の確立が求められます。
業務効率化とコスト削減を実現するRPA受託開発サービス。低コストで高品質なRPAソリューションを提供し、企業の成長をサポート! 採用難や業務自動化などの効率化をお考えの方はこちら
内製化の具体的な手順
実際にRPAを内製化する場合の一連の流れを、ステップごとに解説します。
内製化を進めるには、まず自社に適したRPAツールの選定と担当者の配置が必要です。その上で、具体的な業務選定から設計、テスト、運用に至る各ステップで現場との連携と改善が欠かせません。特に、小さな成功体験を積みながらシナリオを拡張していくことが、後々のスケールアップを円滑にするポイントです。あらかじめ運用保守を見越して、開発段階から柔軟性を意識した設計を行うのも有効なアプローチとなります。
Step1:自動化対象業務の洗い出し
まずは業務全体を棚卸しし、繰り返し作業や人的ミスが発生しやすい部分を優先的に探索します。データ入力や定型処理など、標準化されやすい手順がある業務を見つけることが重要です。洗い出し作業では、現場担当者へのヒアリングや実際の作業観察を行い、必要以上に複雑な工程がないかを確認します。こうした初期の段階を丁寧に行うことで、開発後の手戻りを最小限に抑えられます。
Step2:要件定義とシナリオ策定
自動化対象が決まったら、どのような機能が必要か、どの範囲までロボットに任せるかを明確にします。実際の処理フローを可視化し、分岐条件やエラー対応などの詳細を洗い出してシナリオとして落とし込みます。ここで要件が曖昧なまま進捗してしまうと、途中で大幅に設計を変える必要が生じるリスクがあります。よって、要件定義段階で現場を巻き込み、齟齬をなくすことが欠かせません。
Step3:開発・テストと改善
要件定義をもとに実際のRPAボットを作成し、小さな単位でテストを重ねて動作検証していきます。エラーや処理漏れが見つかった場合は、シナリオの修正や条件分岐の追加など、機能を都度改善しましょう。開発とテストを並行して行うことで、運用開始前に大きな問題を洗い出しやすくなります。開発段階の丁寧な改修が、結果的に運用の安定化にも直結します。
Step4:運用・保守と定期的なフィードバック
シナリオが完成して本格稼働を始めた後も、定期的なモニタリングと保守が欠かせません。業務ルールの変更やシステムのアップデートに伴い、RPAボットを適宜修正して動作の安定を保つ必要があります。また、現場から新たな要望や改善点が出てきた場合は、優先度を見極めながら柔軟に対応できます。こうしたフィードバックサイクルを回すことで、運用効率を最大限に高められます。
残業過多によるSVの負担増とコストの増大、オペレーターのパフォーマンス分析、クライアントレポートのミスリード、架電時のリストコントロール等、多くの課題をRPA導入で改善しました。コア業務への集中ができた背景はこちら
内製化に必要な知識・スキル
RPA開発を円滑に進めるために、基礎知識やコミュニケーション能力が求められます。
RPAの開発では、ツールへの習熟と同時に対象業務の構造を理解する力も重要になります。単純なマウス操作の記録だけでなく、エラー時のフォールバックや複数システム間の連携など、高度な設定が求められる場面もあります。さらに、チームメンバーや現場担当者と密に連携できなければ、要件の取りこぼしや業務プロセスとの食い違いが起こりかねません。技術力と対話力の両面をバランス良く磨くことが、プロジェクトを成功に導くカギとなります。
プログラミングやシステム開発の基礎
RPAツールはノーコードまたはローコードの開発環境を提供するものが多いですが、プログラミングの概念を知っていると効率的に取り組めます。例えば、条件分岐やループ処理、例外処理などは、一般的なプログラミングと共通する要素です。また、システム開発特有のフェーズ管理やバージョン管理の考え方を理解しておくと、開発体制を整備しやすくなります。
業務プロセス構築・分析のスキル
RPAは特定のタスクを自動化するだけでなく、業務全体の流れを踏まえて効果的に配置することが鍵となります。現行の業務フローを可視化し、不要な作業を排除することで、より高い効率化を実現できます。分析結果を踏まえてシナリオを設計するには、顧客対応やバックオフィスなど、多岐にわたる現場の動きを把握する力が必要です。
チーム内での調整力とコミュニケーション
開発担当の視点と現場担当の視点が一致しないままプロジェクトが進むと、完成後に機能面でズレが生じやすいです。定期的なミーティングや進捗報告の場を設け、双方の意見を調整しながら作業を進めることが重要になります。特に要件定義段階やテスト段階でコミュニケーションを密に行うことで、実運用に必要な機能や細かい調整点をスムーズに把握できます。
RPA内製化の導入事例
ニッセンはRPAの導入により、年間2,160時間の業務時間を削減し、約1億円のコスト効果を達成しました。これにより、スーパーバイザー(SV)を担う社員の過剰な残業の改善、ヒューマンエラーの排除、リスト管理の自動化など、単なる時間やコストの削減以上の効果が得られました。
残業過多によるSVの負担増とコストの増大、オペレーターのパフォーマンス分析、クライアントレポートのミスリード、架電時のリストコントロール等、多くの課題をRPA導入で改善しました。コア業務への集中ができた背景はこちら
内製化か外注か?判断のポイント
どちらの方法が自社に合っているか、判断するために考慮すべき要素をまとめます。
自社のリソースや導入目的によって、内製化か外注かを選ぶ最適解は変わってきます。短期的に効果を求めるなら、専門ベンダーに委託してスピーディに開発を進める方が合理的な場合があります。一方、長期的なコスト削減と組織内のスキル豊富化を目指すのであれば、学習コストや工数をかけても内製化を選ぶ価値は大きいです。ここでは、それぞれの視点から判断材料を確認してみましょう。
コスト・スピード面を比較する
外注は初期コストがかかる反面、短期的に仕組みを整えられるため、早期のROIに期待が持てます。内製化は開発に時間がかかる場合があるものの、ノウハウが蓄積されれば外注費用がかからなくなるため、長期的なコストパフォーマンスに優れます。自社の経営計画や投資回収期間を考慮したうえで、どちらの選択肢に軍配が上がるのかを検討することが大切です。
社内リソースと運用期間を考慮する
内製化を成功させるには、RPA開発担当および運用保守を担うメンバーを確保する必要があります。また、RPA化による効果を最大化するには、長期的な運用とスキル蓄積のサイクルが求められます。もし短期間だけの自動化が目的であったり、社内に開発を担う人材がいない場合は、外注を活用するほうが現実的な選択かもしれません。最適な導入形態は、自社の将来的なビジョンやリソース状況によって変動する点を理解しましょう。
業務効率化とコスト削減を実現するRPA受託開発サービス。低コストで高品質なRPAソリューションを提供し、企業の成長をサポート! 採用難や業務自動化などの効率化をお考えの方はこちら
RPA内製化の失敗事例・成功の秘訣
内製化におけるよくある失敗例から学び、成功経験を活かすことでプロジェクトを軌道に乗せられます。
失敗の背景には、要件定義やツール選定が曖昧なままプロジェクトを進めてしまったことや、社内で過度に属人化した運用を行っていたケースが挙げられます。早期から現場との連携を密に取り、導入目的とメリットを共有することが重要です。一方、少しずつ小規模な業務から導入を始めて社内理解を深め、ノウハウの蓄積後に対象範囲を拡大する成功事例も多く存在します。計画的かつ段階的にRPAを社内へ定着させることで、継続的な効果が期待できます。
よくある失敗パターンと対策
プロセスや要件がはっきりしないままRPAツールを導入すると、想定外の手戻りが頻発します。また、ツールの特性と合わない複雑な作業を無理にRPA化しようとした結果、機能過多のボットが生まれることもあります。
弊社も、内製化の初期段階ではエンジニアがいませんでしたので、某RPAコンサルタントに伴走いただき内製化を支援していただきましたが、初期コスト含め数百万の投資が発生したり、ツールのリプレイスを行う決断も必要になったりと思い通りにはいかないケースがありました。
対策としては、導入前の目的や業務分析をしっかり行い、本当に自動化が有効な部分を見極めることが大切です。ツール選定においても実証テストを実施し、自社の要件と合致するかを事前に確認しましょう。
成功事例に学ぶポイント
段階的に導入を進め、トライアルで得た成功体験を周辺部門に展開していく手法が効果的です。まずは範囲の小さい部門や明確な作業手順がある業務から始めることで、早期に成果を確認でき、メンバーのモチベーション向上にもつながります。ノウハウを共有しながら徐々に拡大を図るアプローチは、リスクを最小化しつつ社内全体にRPAを浸透させる良い方法と言えます。
残業過多によるSVの負担増とコストの増大、オペレーターのパフォーマンス分析、クライアントレポートのミスリード、架電時のリストコントロール等、多くの課題をRPA導入で改善しました。コア業務への集中ができた背景はこちら
RPA内製化にかかるコスト・価格相場
RPAを内製化する際に想定される費用構成を把握し、予算計画を立てておきましょう。
RPAは導入が安価に感じられる一方、実際には継続的な運用コストや人材育成費がかかる点に注意が必要です。社内での開発や運用を軸に据えるなら、開発用PCやライセンス、トレーニング予算など、はじめから全体像を把握しておくことが大切です。また、運用フェーズに入ってからも保守やバージョンアップ対応などの追加の費用が発生するため、ある程度の余力を持った予算計画を用意しておくことが望ましいです。
ツール導入やライセンス費用
RPAツールの種類によっては、初期導入費用だけでなく月額や年額のライセンス料が発生するケースもあります。シナリオを複数稼働させるためには追加のライセンスやボット数の契約が必要になる場合があるため、想定する規模に合わせたライセンス体系を選びましょう。コストを抑えるなら、必要最低限のライセンスで小規模から始め、後から拡大する方法も考えられます。
人材育成・トレーニングのコスト
内製化の肝である人材育成には、技術的な勉強会や外部セミナーの受講費が必要になることがあります。小規模な集合研修で足りる場合もありますが、実践的なスキルを身につけるにはプロジェクトを通して学ぶOJTの方が効果的な場合も多いです。どの形態が自社の文化に合うかを検討しながら、将来を見据えて育成計画を作成することが重要になります。
運用・保守の追加費用
RPAは導入して終わりではなく、運用時に発生する問題対応やシナリオ調整による改修作業を継続して行う必要があります。バージョンアップがあるツールの場合、適宜対応しないと機能不全が起きる可能性もあるため、保守契約などで費用が追加発生することがあります。安定的な稼働を維持するための運用体制を整えつつ、こうしたコストを中長期で見込んだ予算編成を心がけましょう。
業務効率化とコスト削減を実現するRPA受託開発サービス。低コストで高品質なRPAソリューションを提供し、企業の成長をサポート! 採用難や業務自動化などの効率化をお考えの方はこちら
RPAか内製か外注(委託)かをお悩みであればニッセンへ
RPAの内製化は、長期的な運用効率や社内のDX促進に寄与する反面、人材育成や開発工数といった課題もあります。自社の目的やリソースを考慮し、最適な導入形態を選択しましょう。
ニッセンでは、低コストで小規模でも対応できるRPAの制作代行を行っております。まずは御社の課題をヒアリングさせていただき、無料でコスト削減シミュレーションをさせていただきます。内製か外注(委託)かをお悩みであれば、一度弊社にご相談くださいませ。じっくりと比較検討いただくことが可能です。お気軽にお問い合わせくださいませ!
業務効率化とコスト削減を実現するRPA受託開発サービス。低コストで高品質なRPAソリューションを提供し、企業の成長をサポート! 採用難や業務自動化などの効率化をお考えの方はこちら